 |
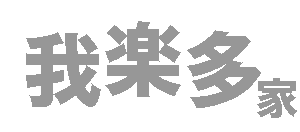 石川の祭り |
|
このページでは、私が撮影した石川県の祭りやイベントなどが年間の開催順にご覧になれます。
石川県の能登半島では夏から秋にかけて数mから十数mのキリコと呼ばれるものを数十人で担ぐという独特の祭りが多くの地区で行われます。 キリコは地域によって奉燈(ほうとう)やオアカシとも呼ばれ、その形や担ぐときの掛け声、太鼓にも多少違いがあります。 石川県内にはキリコ祭り以外にも他の地域では見られないようなちょっと珍しい祭りが多数あります。 最近では、祭りが毎年決まった日ではなく土日に行わることが多くなっており、また天候によっては中止や順延される場合もあります。 お出かけになる時は、各地の役場や観光協会などに日程を確認するとよいでしょう。 それと県内の祭りは見物人に対してほとんど規制を行っていません。 動いているキリコや山車のすぐ傍で見たり写真を撮ったりすることもできないことはありません。 ですがキリコや山車は予想外の動きをすることがあり非常に危険です。 十分すぎるくらいの注意力を持って、そして祭りの運行の妨げにならないように祭りを見物して下さい。 なお、以前は自作の動画も掲載していましたが画質が悪く、最近では大概、YouTubeなどで見ることができるので、Niftyのホームページ規約が変更になったこともあり掲載をやめました。 ですが多数の祭りをDVD-Rに収録した「石川の祭り・総集編 改訂第二版」を発送するサービスを行っていますのでご利用ください。 左の写真をクリックすると各祭りに関するページが表示されます。 |

|
新年奉納花火 1月1日。 石川県羽咋市寺家町気多大社で1月1日午前0時から行われる「新年奉納花火」です。 新年を祝って気多大社を望む海岸で15分ほどの間に約1000発の花火が打ち上げられます。 花火の中には♡の形のものがあり、縁結びの神様でも知られる気多大社らしさを感じます。 年末年始は気多大社付近は交通規制がありますのでご注意ください。 |

|
皆月あまめはぎ 1月2日。 石川県輪島市門前町皆月で1月2日に行われる国指定無形文化財の「あまめはぎ」です。 奇怪な面様を付け木槌を打鳴らした若衆が地区内の家を回りながら怠け者や親の言うことを聞かない子供を戒めて歩きます。 「あまめ」とは、囲炉裏で暖を取りすぎると脛にできる火だこのことで怠け者を称しています。 |

|
彌榮太鼓初打奉納 1月7日。 石川県鳳珠郡能登町宇出津八坂神社で1月7日午前0時から行われる「彌榮太鼓初打奉納」です。 神社で神事を行った後、境内に設けられた舞台で彌榮太鼓保存会の若衆が奇怪な面を付けて太鼓打ち奉納を行います。 激しく太鼓を打鳴らす若衆には時折水がぶっかけられ、その度により激しさを増します。 |

|
曽々木寒中みそぎ 1月第3土曜日。 石川県輪島市町野町曽々木で毎年1月第3土曜日に行われる「曽々木寒中みそぎ」です。 曽々木海岸の窓岩ポケットパークで曽々木キリコ太鼓や獅子舞、御陣乗太鼓などが披露され、そして下帯姿の青年団の若衆が神輿を担いで海に入る「海中みそぎ」神事が行われます。 |

|
雪だるままつり 2月上旬。 石川県白山市桑島地区と白峰地区で2月上旬に行われる「雪だるままつり」です。 雪だるままつりは、桑島地区と白峰地区で別々の日に1日ずつ行われ、1人1個以上を目標に家々で雪だるまを作って飾り、夜は、ロウソクを灯して幻想的な空間をつくり出します。 |

|
石仏山祭り 3月2日。 石川県鳳珠郡能登町柿生で3月2日に行われる「石仏山祭り」です。 石仏山は今も女人禁制の「結界山」であり、山中にある高さ3m、幅60cmの「前立ち」と呼ばれる柱状巨石で神事が行われます。 社殿建築が出現する以前の原始神道の形を今にとどめているとされ、「お山」が「山の神」「田の神」として信仰された神体山としての古い形態を残している神事です。 |

|
的打ち神事 3月15日。 石川県珠洲市三崎町寺家で3月15日に行われる「的打ち神事」です。 須須神社金分宮で神事を行い、菱餅を参拝者にまいた後、境内で宮司が東西南北の一方向づつ弓を構えては的に向かって計四回矢を放ちます。 矢が的に当たるといい年になるとされ、参拝者の氏子らも的打ちに挑戦することができます。 県内ではこの時期、数地区で餅まきなどの春祭りが行われます。 |

|
蛇の目神事 4月3日。 石川県羽咋市寺家町気多大社で4月3日に行われる「蛇の目神事」です。 大国主神が邑知潟の大蛇を退治したという故事にちなみ、大蛇の目に見立てた和紙の●を神職が弓、槍、太刀で射るという神事が行われます。 的にした和紙は厄よけになると言われ神事が終わると皆、破って持っていきます。 その後、流鏑馬神事が行われる年もあるようですが馬の用意が難しく最近は行われていないそうです。 |

|
弓ひき祭 4月3日。 石川県鳳珠郡能登町十郎原の日桂神社で4月3日に行われる「弓ひき祭」です。 都落ちした平家の一族が十郎原西谷地区に住み着いたのが祭りの起源とされ、数名の氏子が鎧甲姿で神事を行った後、稲作の豊穣を祈って田に向かって奉射します。 そして次に境内に用意した的に向かって順に矢を放ち、的中すれば豊作になるという言い伝えがあります。 |

|
鯖踊り神事 4月4日。 石川県鳳珠郡穴水町木原で4月4日に行われる「鯖踊り神事」です。 神輿が地区内を廻って神社に戻ると神事が行われ、その後、神社の拝殿内をまな板に塩サバと包丁を乗せて飛び跳ねる「鯖踊り神事」が行われます。 昔、悪さを働く狢を、好物の鯖を置き、包丁で斬りつけて退治したことから始まった祭りだと言われているそうです。 |

|
輪島曳山祭・住吉神社祭 4月4、5日。 石川県輪島市鳳至町で4月4、5日に行われる「輪島曳山祭・住吉神社祭」です。 住吉神社祭は4日に宵宮祭、5日に曳山祭を行います。 宵宮祭では、カラオケ大会や太鼓演奏などのイベントを行うようです。 曳山祭では、人形と造花を飾った曳山が14時頃神社を出発し18時頃まで地区内を巡行します。 |

|
輪島曳山祭・重蔵神社祭 4月5、6日。 石川県輪島市河井町で4月5、6日に行われる「輪島曳山祭・重蔵神社祭」です。 重蔵神社祭は5日に宵宮祭、6日に曳山祭を行います。 宵宮祭では、カラオケ大会や太鼓演奏などのイベントを行うようです。 曳山祭では、人形と造花を飾った曳山が午前9時頃神社を出発して夕方まで地区内を巡行します。 |

|
チャンチキ山祭 4月中旬日曜日。 石川県七尾市街地西部で4月中旬の日曜日に行われる「チャンチキ山祭」です。 この祭りは、青柏祭のでか山に対して小さい曳山なので「ちょんこ山祭り」と呼ばれたり、「曳山奉幣祭」と呼ばれたりもするそうです。 人形を飾った6基の曳山が地区内を巡行します。 2001年は風が強く、曳山の傘が取り外されていたのが残念でした。 |

|
宇出津曳山祭 4月第3土、日曜日。 石川県鳳珠郡能登町宇出津で4月の第3土、日曜日に行われる「宇出津曳山祭」です(2000年までは4月18,19日に行われていました)。 人形を飾った2基の曳山が地区内を巡行し、宇出津駅前や役場前に集合して獅子舞などを行います。 青柏祭のでか山と比べる程ではありませんが、たぶん現在では能登のこの形の曳山としては、でか山についで大きいような気がします。 |

|
田鶴浜曳山祭り 4月第4土曜日。 石川県七尾市田鶴浜町で4月の第4土曜日に行われる「田鶴浜曳山祭り」です。 朝、神社に集合した舟形の曳山1基を含む人形を飾った6基の曳山が地区内を夜遅くまで巡行します。 夜には太鼓が披露され、深夜、ヨイヨイの掛け声と木遣り歌が町に響き渡る様は風情があります。 |

|
小木伴旗祭り 5月2、3日。 石川県鳳珠郡能登町小木港で5月2、3日に行われる「小木伴旗祭り」です(数年前までは4月17、18日に行われていました)。 五色の吹流しを付けた大のぼり旗を立てた十艘の伴旗船が笛や鐘・太鼓に合わせて小木港をパレードします。 3日は、御座船(大型の船)に神輿を乗せ、全ての伴旗船を引っ張り1列でパレードし、小木港は華やかに彩られます。 |

|
青柏祭 5月3、4、5日。 石川県七尾市街地で5月3日、4日、5日に行われる「青柏祭」です。 鍛冶町、府中町、魚町の三町から「でか山」と呼ばれる高さ12メートルの3基の曳山(山車)が道路ギリギリに曳き回されます。 曳山の見所である狭い街角で行われる辻廻し(方向転換)は見逃せません。 4日は大地主神社で、5日は食菜市場前道路などで3基のでか山が勢揃いします。 |

|
お旅まつり 5月5月第2金、土、日曜日。 石川県小松市街地で5月5月第2金、土、日曜日に行われる「お旅まつり」です。 本折日吉神社と莵橋神社の春季祭礼で漆塗りや金箔の豪華な8基の曳山(山車)が曳き回されます。 曳山は舞台になっており子供歌舞伎が演じられます。 以前は、各町内でそれぞれ行っていたそうですが、数年前から第2土曜日に8基の曳山を全て集合させ、子供歌舞伎を披露するようになりました。 |

|
御田植神事 5月26日。 石川県白山市若宮の若宮八幡宮の春祭りで5月26日に行われる「御田植神事」です。 御田植神事は、若宮八幡宮の春祭りで行われる神事の1つで大正初期から毎年5月26日に行われており、神饌田(しんせんでん)で豊穰を願って田植え唄が歌われる中、早乙女が古式ゆかしく横並びで田植を行い、田植え踊りも奉納されます。 |

|
あばれ祭り 7月第1金曜日。 石川県鳳珠郡能登町宇出津で7月第1金、土曜日に行われる「あばれ祭り」です。 金曜日は、日中、町内を練り歩いていた40本余りのキリコが花火大会の後、5本の大松明のまわりに集結し、座布団や手拭いで火の粉を払いながら太鼓や鐘、笛の音とともに乱舞します。 |

|
あばれ祭り 7月第1土曜日。 石川県鳳珠郡能登町宇出津で7月第1金、土曜日に行われる「あばれ祭り」です。 土曜日は、キリコに守られるように進む2台の神輿が八坂神社へ向かう道中、道路や海、川、炎に叩き付けられ、これでもかと言わんばかりに叩き壊されていきます。 壊れ方が酷い程、神様が喜ぶとされ、当然のことながら神輿は毎年新調されるそうです。 |

|
互市祭 7月第1土曜日。 石川県七尾市府中町で7月第1土曜日に行われる「互市祭」です。 印鑰神社(いんにゃく神社)の祭礼で14本程の奉燈が担ぎ出され、午後7時半頃、市役所近くの市道1号線に勢揃いします。 その後、各奉燈は印鑰神社に進み乱舞します。 印鑰神社に集まった奉燈は神社でお払いを受けた後、各地区に戻ります。 |

|
七尾祇園祭 7月第2土曜日。 石川県七尾市街地東部で7月の第2土曜日に行われる「七尾祇園祭」です。 大地主神社(山王神社)の祭礼で「東のおすずみ」と呼ばれています。 氏子12町から十数本の奉燈が担ぎ出され、午後8時頃、湊町の仮宮前広場で乱舞した後、大地主神社へと進みます。 そして午後11時頃、大地主神社の境内せましと乱舞します。 |

|
真脇キリコ祭り 7月中旬土、日曜日。 石川県鳳珠郡能登町真脇で7月中旬の土、日曜日に行われる「真脇キリコ祭り」です。 8、9本のキリコが地区内を練り歩きます。 真脇のキリコは、提灯、花、短冊、吹流しなどで艶やかに飾り立てられています。 祭り初日、全てのキリコが橋の上に並ぶと花火が打上げられます。 |

|
おさよ祭り 7月海の日前の土、日曜日。 石川県輪島市門前町剱地で7月の海の日前の土、日曜日に行われる「おさよ祭り」です。 子供や女性が担ぐキリコを含めた大小のキリコ数本とオイル缶を叩き鳴らす女の子たちを乗せた山車、そして太鼓が地区内を巡行します。 おさよという娘の悲恋と祀られた二人が年に一度再会するという言い伝えから「おさよ祭り」と言われるそうです。 以前は、8月21、22日に行われていました。 |

|
長谷部まつり 7月第3日曜日。 石川県鳳珠郡穴水町でたぶん7月第3日曜日に長谷部信連を偲んで行われる「長谷部まつり」です。 百万石行列を小規模にしたような武者行列が日中行われ、夜には灯籠流しや花火大会が行われます。 |

|
松波人形キリコ祭り 7月第4土曜日。 石川県鳳珠郡能登町松波で7月の第4土曜日に行われる「松波人形キリコ祭り」です(数年前までは7月15日に行われていました)。 全てのキリコに手作りの武者人形などを飾り、松波神社に13時頃集合し神輿を迎えた後、町内を練り歩きます。 15時頃、福祉センター前で人形審査を行い、夜は中央交差点の四方に9本のキリコが集合し、1本づつキリコが競い合うように乱舞します。 |

|
どいやさ祭 7月第4土、日曜日。 石川県鳳珠郡能登町姫で7月の第4土、日曜日に行われる「どいやさ祭」です。 6基の袖ギリコと神輿が地区内を進行します。 見所は初日の夜で、かがり火を焚いて袖ギリコが乱舞したり海上渡御などが行われるそうです。 袖ギリコは、奴(やっこ)が袖を拡げた姿に似ていることから袖ギリコと呼ばれるという説があります。 |

|
名舟大祭 7月31日、8月1日。 石川県輪島市名舟町で7月31日、8月1日に行われる「名舟大祭」です。 31日の夜、神輿が海に立つ鳥居で神を迎えた後、御陣乗太鼓が奉納され、5本のキリコが神輿と共に地区内を練り歩きお仮屋へと向かいます。 1日の昼、神輿が海に立つ鳥居で神送りを行った後、御陣乗太鼓が奉納され神輿が神社に戻って祭りを終えます。 1日は、キリコが出ないで太鼓山車が神輿を先導します。 |

|
松任まつり 8月上旬。 石川県白山市倉光の松任総合運動公園で8月上旬の第1日曜日を含む数日間に行われる「松任まつり」です。 日曜日は、虫送り太鼓と日本一と言われる巨大な俵型の大松明2基、中松明4基が総合運動公園に集結し火祭りが行われます。 他の日には薪能や浴衣姿の踊子が商店街を踊り流します。 |

|
ちょんがりまつり 8月6日。 ちょんがりまつりは、8月上旬に行われる珠洲まつりの幕開けとして8月6日に石川県珠洲市飯田港広場で行われ、高さ14m、直径7mの日本一と言われる大提灯を中心にちょんがり踊りなどが行われます。 |
| 皆月山王祭 8月10、11日。 石川県輪島市門前町皆月で8月10、11日に行われる「皆月山王祭」です。 日吉神社から午前10時頃出発した吹流しを付けた曳山が地区内を巡行し、10日は海岸沿いの道路に設置された御仮屋で、11日は日吉神社境内で馬駆け神事などが行われます。 残念ながら2001年、2002年は、馬の確保ができず馬駆け神事が中止されました。 |

|
一向一揆まつり 8月中旬。 石川県白山市別宮町の白山市鳥越支所周辺で8月中旬に行われる「一向一揆まつり」です。 一向一揆まつりは、鳥越村の山里に「百姓ノ持チタル国」として織田信長に最後まで抵抗した山内(やまのうち)衆の偉業を偲んで開催され、一向一揆・仮装行列、和太鼓の競演、踊りの夕べ、花火大会などが行われます。 |

|
砂取節祭り 8月13日。 石川県珠洲市馬緤で8月13日に行われる「砂取節祭り」です。 砂取節まつりは、8月上旬に行われる珠洲まつりの最後を飾ります。 馬緤海岸傍の会場で祭り太鼓の演奏やじゃんけん大会などが行われ、砂取節輪おどりの後、花火大会も行われます。 |

|
新宮納涼祭 8月14日。 石川県七尾市中島町藤瀬で8月14日に行われる「新宮納涼祭」です。 藤津比古神社に集結したキリコ9本が午後9時頃、神輿と共に神社を出発しお旅所(川原)へと向います。 お旅所では鉦と太鼓に合わせてゆっくりとキリコが神輿を中心に回ります。 神社も途中の道もお旅所も非常に明かりは少なく、他の勇壮な祭りと違い、神社でのキリコの差し上げ以外は静かで幻想的な祭りです。 |

|
天領祭 8月17、18日。 石川県輪島市門前町黒島町で8月17、18日に行われる「天領祭」です。 子供奴振り行列、神輿、大阪城と名古屋城をかたどった2基の曳山が町内の北側と南側に分けて二日間巡行します。 藩政期、黒島は天領地であり、北前船で賑わった面影が感じられます。 残念ながら2001年は、少子化のために子供奴振り行列が中止されました。 |

|
大沢町夏祭り 8月17、18日。 石川県輪島市大沢町で8月17、18日に行われる「大沢町夏祭り」です。 静浦神社から神輿1基と傘鉾を立て人形や吹流しで華やかに飾られた1基の曳山が海岸のお旅所を中心に長手地区と西出地区をそれぞれ二日間曳き回されます。 海岸線の道路で曳山と神輿が押し合う様は珍しく、見所です。 |

|
曽々木大祭 8月17日。 石川県輪島市町野町曽々木で8月17日に行われる「曽々木大祭」です。 春日神社に集合した5本のキリコが神事を済ませた後、花火が名勝窓岩から打ち上げられる中、窓岩ポケットパークで太鼓が打鳴らされキリコが乱舞します。 |

|
沖波大漁祭り 8月中旬。 石川県鳳珠郡穴水町沖波で8月中旬に行われる「沖波大漁祭り」です。 二日目の朝、5本のキリコが立戸の浜の海で乱舞することは有名ですが、初日の深夜、恵比須崎の恵比須神社(御堂)の周りを太鼓を乱打し、キリコが駆け回る様も迫力があり見逃せません。 以前は、8月17、18日に行われていましたが、現在は8月中旬の夜と翌日の朝に行われるようです。 |

|
藤之瀬祭り 8月17、18日。 石川県鳳珠郡能登町藤之瀬で8月17、18日に行われる「藤之瀬祭り」です。 上藤之瀬・下藤之瀬・吉尾の三地区より大小5本のキリコが担ぎ出される祭りで姫瀧神社・火宮神社の2つの神社を行き来します。 上藤之瀬のキリコは能都町で最大のものだそうです。 神社に向かう狭く暗い山道をロウソクを灯したキリコが担がれて進む姿は幻想的です。 |

|
福浦祭り 8月第4土曜日。 日本最古の木造灯台のある石川県羽咋郡志賀町福浦港で8月の第4土曜日に行われる「福浦祭り」です。 神輿を乗せた船が福浦港の海を渡御するという特色のある祭りで、その後、神輿は御明かし(キリコ)、太鼓、鉦、天狗と共に地区内を巡行し、神社へと進みます。 |

|
酒見大祭 8月第4土曜日。 石川県羽咋郡志賀町酒見で8月の第4土曜日に行われる「酒見大祭」です。 のぼり旗、神輿、山車、御明かし(キリコ)が太鼓、鉦、天狗と共に地区内を巡行してお仮屋の四辻の宮へと進みます。 夜は、御明かし(キリコ)の担ぎ手が真っ暗な道を足を踏み外しながら神輿と共に少彦名神社へと帰り、神社の境内で乱舞します。 |

|
ぐず焼まつり 8月27、28、29日。 石川県加賀市動橋町で8月27、28、29日に行われる「ぐず焼まつり」です。 初日、十メートルの巨大なグズ(魚のお化け)や中グズ、子供グズの造りものが町内を練り廻されます。 神社を出発したグズは、JR動橋駅、小学校前などで激しく乱舞し、巨大グズは、午後10時頃神社に戻って焼却退治されます。 二日目、三日目は、花火大会や獅子舞などが行われます。 |

|
春日野キリコ祭り 9月6、7日。 石川県珠洲市宝立町春日野で9月6、7日に行われる「春日野キリコ祭り」です。 7本のキリコ(小キリコ1本含む)が初日、各地区をそれぞれ練り歩き、二日目、神輿渡御が行われ、国道に全てのキリコが揃い、時々、神輿とキリコの練り合いが行われます。 夜、宿神社で全てのキリコと神輿が一緒に威勢よく練り回った後、獅子舞が奉納されます。 |

|
安宅まつり 9月7、8、9日。 石川県小松市安宅町で9月7、8、9日に行われる「安宅まつり」です。 重さ1.5トンの金色の神輿が町内を渡御し、県内ではここだけという恵比須や大黒天などの像を乗せた曳船が木遣り歌とともに町内を練り廻り、勇壮な獅子舞も町内を廻ります。 曳船は北前船で栄えた昔をしのんだもので船名旗を数本立てています。 期間中には花火大会も行われ、最終日には安宅輪踊りも行われるそうです。 |

|
笠師祭 9月第2土曜日。 石川県七尾市中島町笠師で9月の第2土曜日に行われる「笠師祭」です。 猿田彦に先導された3基の末社神輿と1本の枠旗が鉦、太鼓を鳴らしながらそれぞれの神社氏子ごとに集まってお旅所のシイザキまで渡御します。 お旅所ではお練りの後、3基の神輿を並べて神事を行い、今度は社名旗、猿田彦、鉦太鼓、神輿、枠旗ごとにまとまって地区内を巡行しながら御招待宅を廻って神社に戻ります。 |

|
蛸島キリコ祭り 9月10、11日。 石川県珠洲市蛸島町で9月10、11日に行われる「蛸島キリコ祭り」です。 16本の豪華なキリコが町内を練り歩き、珠洲ビーチホテル前で一旦集合した後、再び町内を練り歩きます。 11日夜は県指定無形民俗文化財の「早船狂言」が高倉彦神社で披露されます。 雨天の場合は、雨避けのビニールシートでキリコが覆われ運行します。 |

|
大谷キリコ祭り 9月12、13日。 石川県珠洲市大谷町で9月12日に行われる「大谷キリコ祭り」です。 21時頃から動きだした7本ほどのキリコが神輿を挟むように大谷川沿いに広がる地区内を巡行します(大谷には8本のキリコが存在するそうです)。 24時頃、全てのキリコが大谷神社の前に並び、神輿が大谷神社に宮入りするとキリコは各自地区に戻って行きます。 13日は、神輿と獅子舞がくり出されるそうです。 |

|
上戸曳山祭り 9月14日。 石川県珠洲市上戸町で9月14日に行われる「上戸曳山祭り」です。 手作りの見事な人形を飾った3基の曳山が町内を曳き回され、随所で子供達による踊りと歌「きやらげ」が披露されます。 |

|
正院キリコ祭り 9月14、15日。 石川県珠洲市正院町正院で9月14、15日に行われる「正院キリコ祭り」です。 14日夜はキリコが地区内を練り歩き、15日は奴振り道中が神輿や太鼓山車と共に須受八幡神社から地区内を巡行します。 15日の夜、奴振り道中が神社に戻ってくると八幡太鼓が奉納され、神社に集合していたキリコが境内で乱舞しながら各地区へ帰っていくと祭りが終わります。 |

|
柳田大祭 9月16、17日。 石川県鳳珠郡能登町柳田で9月16、17日に行われる「柳田大祭」です。 21時頃、柳田数地区からキリコが白山神社に集合し、5基の神輿と共に神社から数百メートル離れたお旅所へと渡御します。 お旅所では大松明が燃やされ、花火大会も行われます。 残念なことに2001年は4本のキリコが立てられたものの動いたのは最大のキリコを除いた3本だけでした。 |

|
正院川尻曳山祭り 9月18日。 石川県珠洲市正院町川尻で9月18日に行われる「正院川尻曳山祭り」です。 人形を飾った1基の曳山と神輿が地区内を巡行します。 以前は2基の曳山が曳かれていましたが残念なことに2002年は1基のみが曳かれていました。 |

|
引砂・高波キリコ祭り 9月18日。 石川県珠洲市三崎町引砂・高波で9月18日に行われる「引砂・高波キリコ祭り」です。 3本のキリコと神輿が地区内を巡行します。 深夜、神社でキリコが乱舞した後、神輿が入宮するそうです。 |

|
正院小路キリコ祭り 9月19日。 石川県珠洲市正院町小路で9月19日に行われる「正院小路キリコ祭り」です。 3本のキリコと獅子舞、神輿が地区内を巡行し、深夜、神社に戻るとキリコが乱舞し、獅子舞を奉納した後、神輿が入宮します。 獅子舞は、1997年に復活したそうで、子供たちが扮する弁慶と牛若丸が勇壮に舞い、若衆の獅子を退治するというものです。 |

|
杉山キリコ祭り 9月19日。 石川県珠洲市三崎町杉山で9月19日に行われる「杉山キリコ祭り」です。 4本のキリコと神輿が地区内を巡行します。 日中、それぞれの地区を巡行したキリコが21時頃から4本揃って神輿とともに巡行します。 深夜、神社への坂を1本ずつキリコが駆け上がり乱舞し、全てのキリコが境内に並ぶと神輿が火渡りを行って入宮します。 |

|
飯田キリコ祭り 9月20日。 石川県珠洲市飯田町で9月20日に行われる「飯田キリコ祭り」です。 日中、地区内を渡御した神輿が神社に戻ると、10本ほどのキリコも神社に集まり、そして全てのキリコが揃って地区内を練り歩きながら、時々、交差点などで乱舞します。 |

|
狼煙キリコ祭り 9月22日。 石川県珠洲市狼煙町で9月22日に行われる「狼煙キリコ祭り」です。 10mほどの3本のキリコが神輿とともに町内を巡行します。 深夜、市営駐車場で3本のキリコが乱舞し、途中、3本のキリコが1列に並んで前後に動く様は見どころです。 |

|
野々江キリコ祭り 9月25日。 石川県珠洲市野々江町で9月25日に行われる「野々江キリコ祭り」です。 午前中に菅原神社を出発した神輿が7本のキリコと共に地区内を巡行します。 野々江町は広く、途中、野中神社にも寄って神事を行うので、神輿が菅原神社に戻るのは午前3時を過ぎることもあります。 神社に戻ると1本づつキリコが境内で乱舞し、最後に神輿が乱舞して入り宮すると祭りを終えます。 |

|
白丸曳山祭り 9月25日。 石川県鳳珠郡能登町白丸で9月25日に行われる「白丸曳山祭り」です。 人形を飾った2基の曳山が町内を曳き回され菅原神社へと巡行します。 随所で子供達による踊りと歌「きやらげ」が披露され、菅原神社に曳山が戻ると曳手も一緒になって神社の中で「きやらげ」を唄い踊ります。 |

|
いどり祭り 11月7日。 石川県鳳珠郡能登町鵜川で11月7日に行われる「いどり祭り」です。 菅原神社で行われる八百年の伝統のある神事で、2組の氏子当番が持参した小餅と1.2mの大鏡餅の形や質を参列者がいどり(けなす)、それを神主が仲裁します。 今年の収穫で作った餅をいどる(けなす)ことで来年よりいっそうの収穫を願う収穫祭の一種だと思います。 |

|
幸娘みそぎ祓い 12月31日。 石川県羽咋市寺家町の気多大社で12月31日に行われる「幸娘みそぎ祓い」です。 正月三ヶ日だけ気多大社で奉仕する約120人の特別な巫女をしあわせむすめと書いて幸娘(ゆきむすめ)と呼びます。 気多大社で奉仕するにあたり31日、気多大社で集合した後、一ノ宮海岸まで駆け、冬の日本海で「大祓詞」を唱えながら身心を清めるみそぎ祓いを受けます。 |

















































